
ウエイトトレーニングの
プログラムを作成するうえで、
重量、レップ数、セット数などの
変数設定は重要になります。
そしてその変数は
『トレーニングの目的』によって変わってきます。
例えば
アスリートを指導する場合であれば、
試合期に向けて使用重量は上げていきながらも
レップ数は落としていく
『線形ピリオダイゼーション』を
用いることも多いでしょう。
一般的に
ピリオダイゼーションの初期、
使用重量はそこそこで
レップ数が多い時期(8~10レップほどの時期)を
『筋肥大期』と読んだりします。
一方で試合が近づいてきた時期では
使用重量を上げる代わりに
レップ数は少な目(2~5レップ程度)になり、
『最大筋力期』と呼ばれます。
これは筋肥大をするには
重量×レップ数(×セット数)で表される
『総負荷』を高める必要があり、
ある程度のレベルのアスリートの場合は
ある程度の使用重量が必要になるからです。
このように時期によって目的も変わり、
そのため重量、レップ数などの変数も
変化するということは
トレーナーの方には周知の事実でしょう。
今回は、トレーニングにおいて
「重量を上げたほうが良いのか?」
「回数を増やしたほうが良いのか?」
お話したいと思います。
対象によっても適した変数は変わる?
さて、筋肥大が目的の場合、
重量×レップ数(×セット数)で表される
『総負荷』を高める必要があるというのは
先述した通りです。
言い換えると、
『総負荷さえ高めれば
筋肥大はすることが出来る』
とも言えます。
Schoenfeldらのメタアナリシスでは、
高負荷
(60%1RMより大きい負荷)のトレーニングと
低負荷
(60%1RM以下)のトレーニングで、
どちらも挙上不可になるまで実施した場合の
筋肥大、筋力向上への効果を比較しました。
その結果、
最大筋力は高負荷のトレーニングで
より向上した一方で、
筋肥大への効果は高負荷も低負荷も
効果に差はありませんでした。
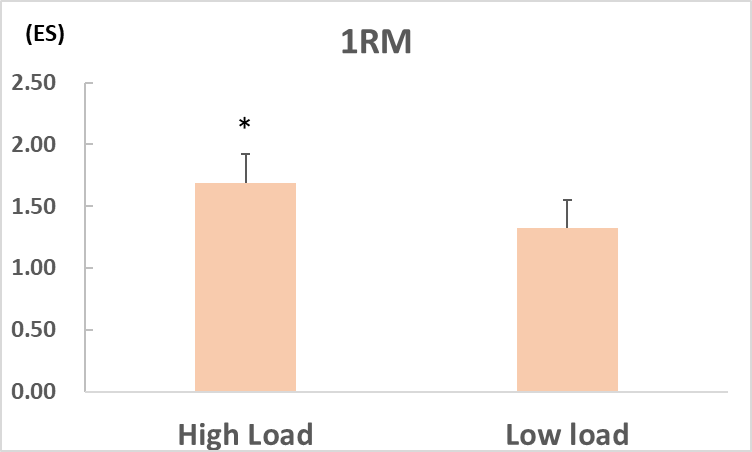
これは高負荷だとレップ数が少なくなる一方で、
低負荷の場合は高負荷よりも
レップ数が多く出来たことで、
結果としてどちらも
『総負荷』を高めることができ、
同程度の筋肥大効果があったと
考えることができます。
では筋肥大を目的にした時期であれば
どちらの方法を用いても良いのでしょうか?
答えは
トレーニングを行っている人の目的によります。
例えば一般の方の身体づくりのように、
筋肥大自体が目的の場合は
好きなほうを選べば良いでしょう。
一方でアスリートの場合は筋肥大をしても
体重に対する相対的な筋力が低下してしまうと
パフォーマンスが下がる可能性が大です。
それに
その後の時期で最大筋力を向上させるのであれば、
筋肥大期にも多少の向上があったほうが
一石二鳥だと思いませんか?
そう考えるとある程度の負荷、
研究にもある通り最低でも60%1RM以上の負荷を
筋肥大期に実施するのがベターでしょう。
一方で
バーベルなどのウエイトが扱えない期間があり、
自重トレーニングしか出来ないといった場合は
自重での低負荷・高ボリュームの
トレーニングを実施するというのはありでしょう。
- 対象の目的
- 今の時期の目的
- 扱える環境
様々な要素を総合的に考え、
適した方法を模索していきましょう!
参考文献
- Schoenfeld, BJ, Grgic, J, Ogborn, D, and Krieger, JW.
Strength and hypertrophy adaptations between low- vs.
High-load resistance training:
A systematic review and meta-analysis.
J. Strength Cond. Res. 31: 3508–3523, 2017.
- 投稿タグ
- ウエイトトレーニング, トレーニング
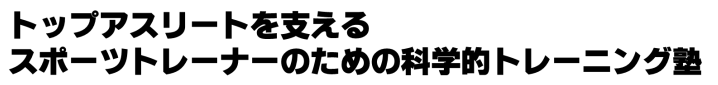






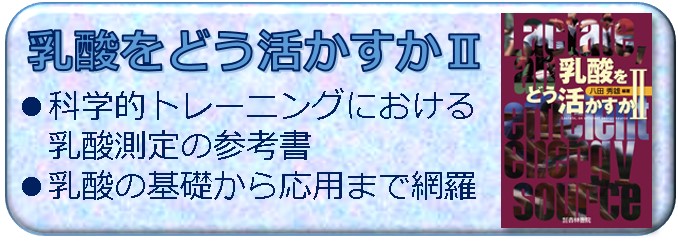


SNSでも配信中