
前回の記事では、
エネルギーの供給機構である
『解糖系』と『有酸素系』を、
2つの工場に例えて、
グリコーゲンが分解される過程の
イメージを紹介しました。
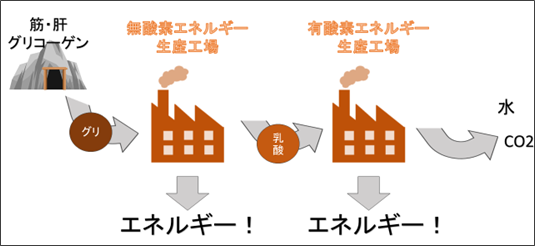
Training Scienceより引用
そして、
エネルギーの供給能力を鍛えるための運動として
- 非常に高い強度の運動で、
無酸素エネルギー生産工場の能力を
高める運動(無酸素持久的トレーニング) - 強度の高い運動を繰り返しながら
グリコーゲンを分解しつつも、
有酸素エネルギー生産工場を
フル稼働させる運動(HIIT) - ある程度の時間維持できる中強度
(LT~OBLA)の運動で、
乳酸が溜まりつつも持続的に行う運動
(中強度持久的トレーニング) - 乳酸が溜まり過ぎない強度
(LTもしくはそれ以下)で
有酸素エネルギー生産工場を
長い時間稼働させる運動(LSD)
などが挙げられるということを紹介しました。
今回は
「強度にメリハリをつけた持久的トレーニング」
というテーマで
具体的な例をご紹介します。
適切な運動の組み合わせ方
有酸素能力を鍛えるための
ベストの方法はどのようなものでしょうか?
先ほど挙げた例でいうと、
LSDが一番有酸素エネルギー生産工場を
長い時間稼働することが出来ますが、
HIITのほうが
稼働時のエネルギー生産量は大きくなります。
はたまたその中間に位置する
中強度の持久的トレーニングで、
ある程度の強度も量も
両立するのが良いのか?
もしくは複数の強度を組み合わせるのが良いのか?
この問いに対する答えの1つとして、
Polarized Trainingというものが挙げられます。
Stoggl&Sperlichの研究では、
48人の持久系アスリートを
以下4つのグループに分けて
その効果を比較しました。
- LSD群(血中乳酸濃度:~2mmol)
- 中強度持久トレーニング群
(血中乳酸濃度:3~5mmol) - HIIT群(90%HRmax~)
- Polarizedトレーニング群
(LSDとHIITの組み合わせ)
その結果、
Polarizedトレーニング群が
他の3群と比較して
有意に疲労困憊時間を延長させたことが
明らかになりました。
有酸素エネルギー供給系に
長い時間負荷をかけ続ける運動(LSD)や、
高い負荷をかける運動(HIIT)単品ではなく、
長い時間負荷をかける運動も、
高い負荷をかける運動も
両方実施するほうが効果的ということになります。
また両方の負荷をかけたいからといって、
間の強度の運動(中強度持久的運動)を
行うのではなく、
メリハリをつけて低強度なら低強度、
高強度なら高強度と
セッションによって
違いを強調したほうに効果があったというのも
面白いところです。
まとめ
様々な強度設定の持久的トレーニングがある中で、
メリハリをつけて低強度、
高強度を処方するのが最も効果的というのは
面白い知見ですよね。
今回紹介したPolarizedトレーニング、
気になった方は是非深堀して
調べて活用してみてください!
- Stöggl, T and Sperlich, B. Polarized training has greater
impact on key endurance variables than threshold, high intensity,
or high volume training. Front Physiol 5 FEB: 1–9, 2014.
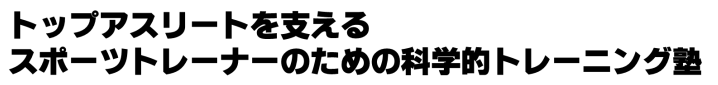






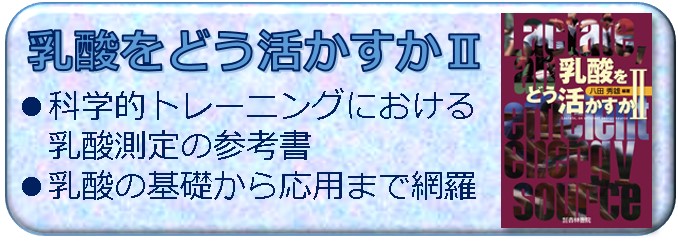


SNSでも配信中