
持久系トレーニングを行ううえで、
強度の設定は非常に重要になります。
基本的な考えとして、
身体にかかる総負荷は
運動強度(速度)×運動量(運動時間)
で決まりますが、
この運動強度と運動量は相反する関係にあり、
強度を上げると
どうしても遂行可能な運動量は落ちてしまいます。
例えば、
ジョギングのような強度の運動だと
1時間走りっぱなしというのも可能ですが、
100m走のペースで
1時間走り続けることは不可能でしょう。
一方で高い強度の運動であっても
レストを挟むことで
ある程度の運動量を確保することが出来ます。
このように持久的なトレーニングを計画する上では
- 強度
- 時間
- レスト時間
- 本数(複数セット実施する場合)
4点の設定が必要になります。
また、そもそも運動を
- ランニングで行うのか?
- バイクで行うのか?
- 水泳などその他の運動で行うのか?
といったことも重要でしょう。
それらの変数を設定する際に、
身体のエネルギー供給系についての
イメージを持っておくことも必要です。
無酸素エネルギーと有酸素エネルギー
筋肉はATPを分解することで
収縮をすることが可能で、
そのATPを再合成は
- ATP-CP系
- 解糖系
- 有酸素系
3つのエネルギー機構が担っているということは、
トレーナーをやられている方ならご存知でしょう。
その中でも
特に解糖系~有酸素系の繋がりをイメージ出来ると、
持久系トレーニングの強度設定に役立ちます。
糖分(グリコーゲン)を分解すると、
乳酸が生成され、
その過程でエネルギーが生産されます。
また、
その乳酸を始めとする物質を
さらに分解することでも
エネルギーが生産されます。
前者を俗にいう解糖系と言い、
後者を有酸素系と言います。
つまりグリコーゲンを最終的に分解する過程で、
解糖系と有酸素系の2段階で
エネルギーを生産するのです。
これは
身体の中に2つの工場があるという
イメージで考えてみると分かりやすいです。
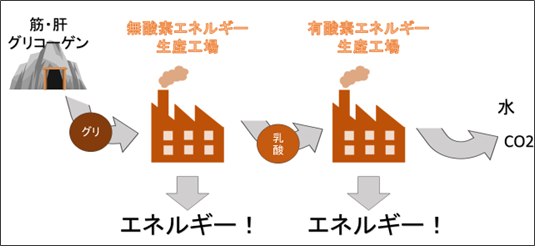
Training Science(http://sasabekouki.com/)より引用
筋肉、肝臓に蓄えられたグリコーゲンを
無酸素エネルギー生産工場で分解し、
エネルギーを生産します。
その過程で乳酸という廃棄物も生産されます。
その乳酸は
有酸素エネルギー生産工場で分解され、
エネルギーを生産します。
エネルギーを生産できるスピードは
無酸素エネルギー生産工場のほうが速いので、
運動強度が高まると
グリコーゲンの分解&乳酸の生産スピードが
上がるものの、
有酸素エネルギー生産工場で
乳酸が溜まり始めてしまいます。
これが、
身体の中で乳酸濃度が上がっているときに
起きている現象です。
そして、
乳酸濃度が2mmolを超える強度を『LT強度』、
乳酸濃度が4mmolを超える強度を
『OBLA』と言います。
目的に合わせた運動強度設定
先ほどのエネルギー生産工場の能力を高めるのが、
持久系トレーニングの目的です。
- 非常に高い強度の運動で、
無酸素エネルギー生産工場の能力を高める運動
(無酸素持久的トレーニング) - 強度の高い運動を繰り返しながら、
グリコーゲンを分解しつつも、
有酸素エネルギー生産工場をフル稼働させる運動
(HIIT) - ある程度の時間維持できる中強度
(LT~OBLA)の運動で、
乳酸が溜まりつつも持続的に行う運動
(中強度持久的トレーニング) - 乳酸が溜まり過ぎない強度
(LTもしくはそれ以下)で
有酸素エネルギー生産工場を
長い時間可動させる運動(LSD)
なんとなくイメージ出来てきませんか?
このイメージを持っておくと、
科学的な手法を用いた
アプローチをしているときにも、
身体の中で起きていることを
大まかに把握出来ます。
是非持久系トレーニングを計画するときには
参考にしてみてください!
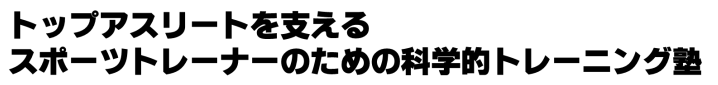






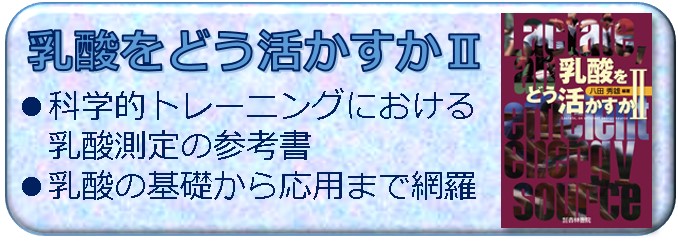


SNSでも配信中